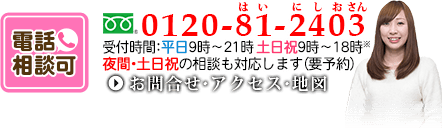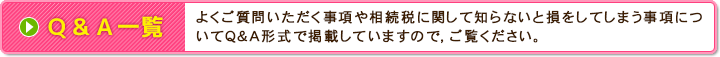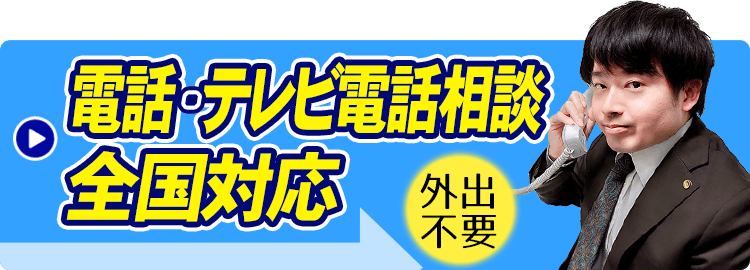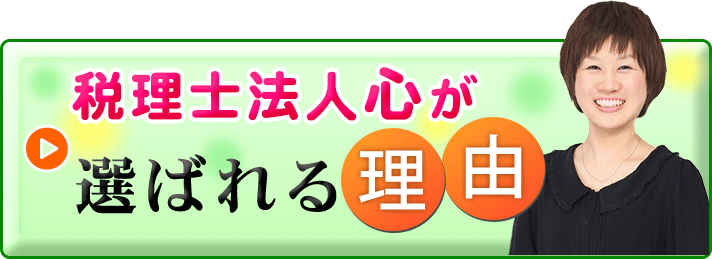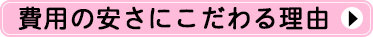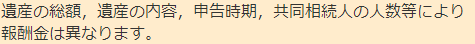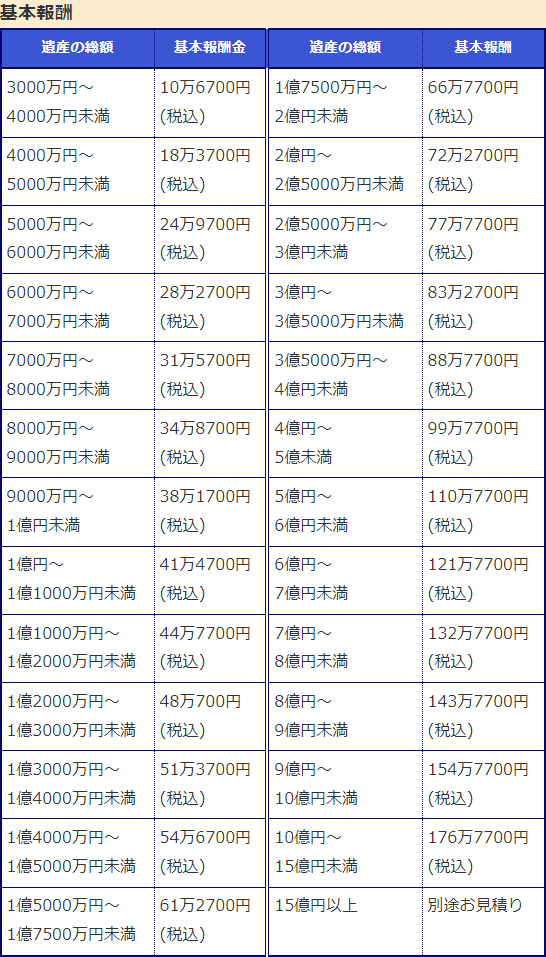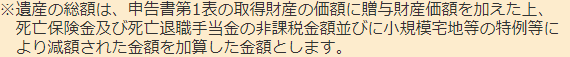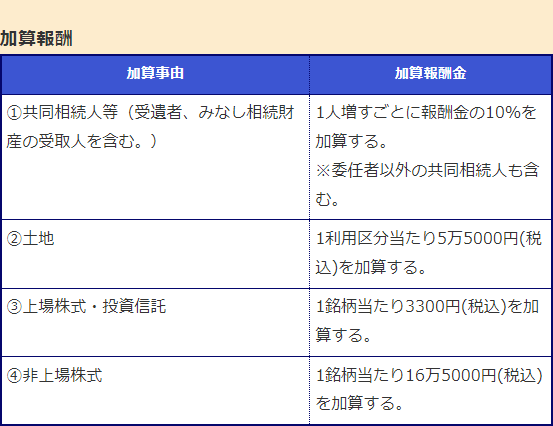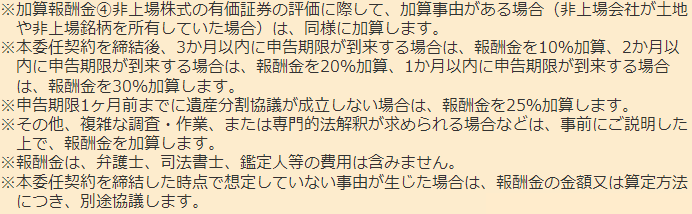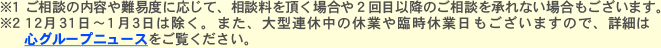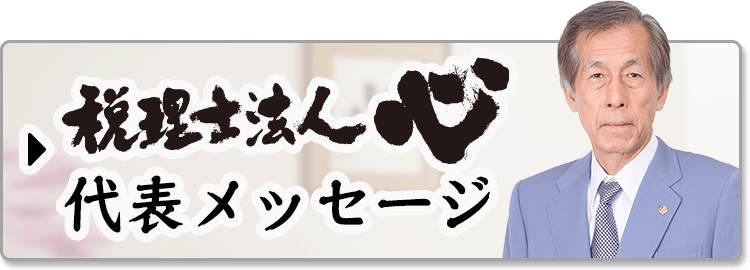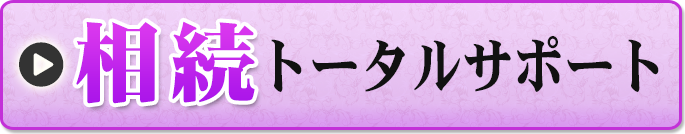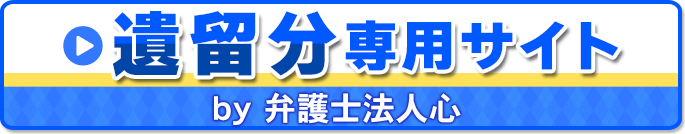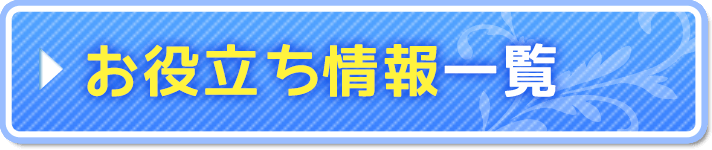お役立ち情報
相続税で2割加算されるのはどのような場合か
1 相続税の2割加算とは
配偶者・子・父母以外の方が、遺産分割や遺言書により財産を引き継いだ場合、相続税が2割加算されます。
このように加算される理由は、配偶者や子などと比べると、その財産を得て生活の元手とすることが予定されていないからなどとされています。
また、孫の場合、通常は親から子、子から孫へと財産を引き継ぐときに2回にわたって課税されるのに、1回しか課税されないのは公平でないと考えられています。
そのため、兄弟姉妹や孫、祖父母、甥・姪などが、遺産を引き継いだような場合には、相続税が2割加算されるのです。
ただし、代襲相続した孫については、本来相続するはずであった子の代わりに孫が相続するので、相続税の2割加算がありません。
2 養子は2割加算の対象となるのか
たとえば、子の配偶者を養子にする場合や、再婚相手の子を養子にする場合などがあります。
このような養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子と認められますので、養子は実子と同じ権利を有します。
そのため、養子は実子と同様で、相続税2割加算の対象となりません。
ただし、孫を養子とする場合には、相続税2割加算の対象となります。
これは、本来なら親から子、子から孫へと2回にわたり相続するところ、1回で孫に渡すことになるため、公平の観点から、養子であっても加算の対象とするというものです。
3 死亡保険金などを受け取った場合
死亡保険金、死亡退職金は相続財産ではありませんが、亡くなったことにより財産を受け取るので相続財産と同じものとみなされ、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
ただし、相続人が生命保険金、死亡退職金を取得した場合は、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、全額が相続税の課税対象となるわけではありません。
しかし、配偶者、子、父母以外の方が取得した場合には、2割加算の対象になります。
たとえば、相続人ではない孫や兄弟が死亡保険金を取得した場合には、そもそも非課税枠の対象とはならず、また2割加算の対象になってしまうため、注意が必要です。
相続税はどのように計算するのか 相続税の課税の対象とならない財産