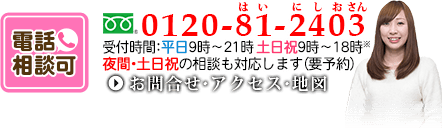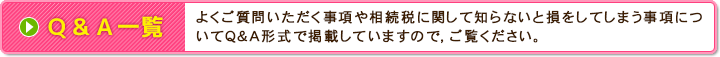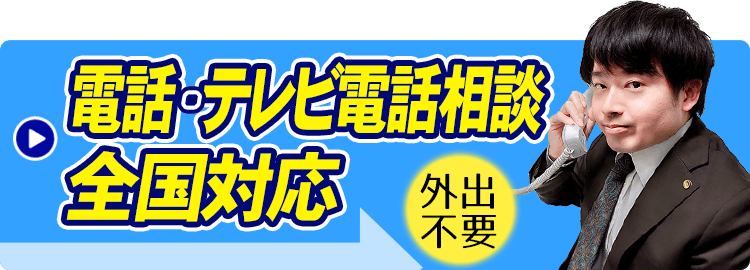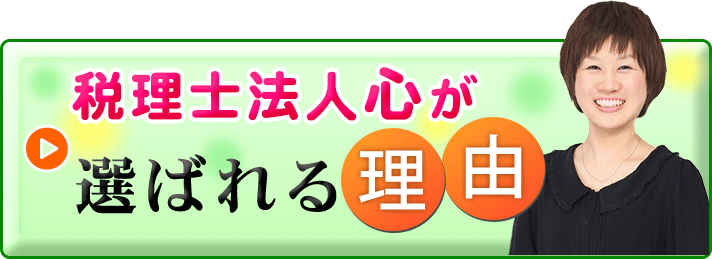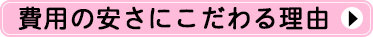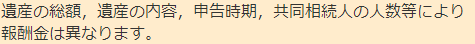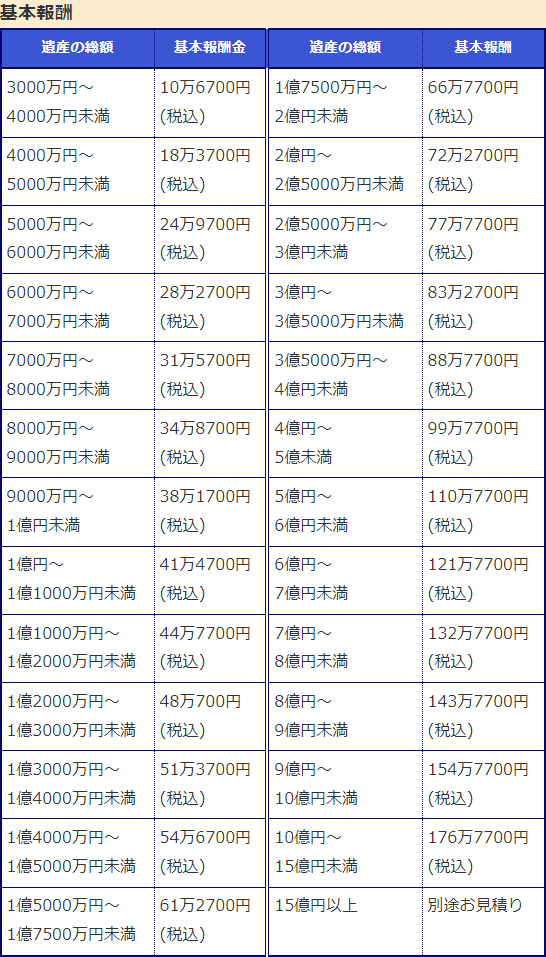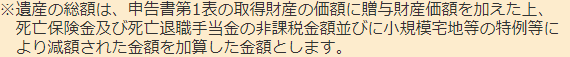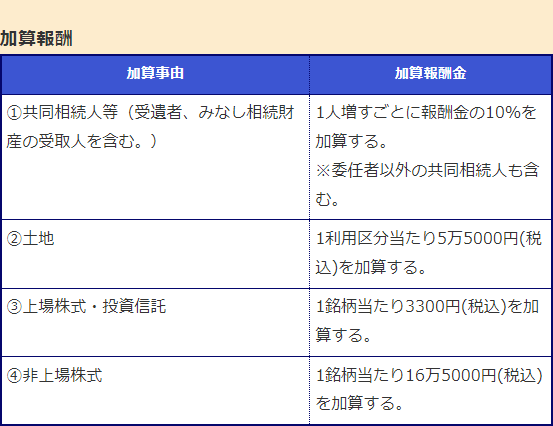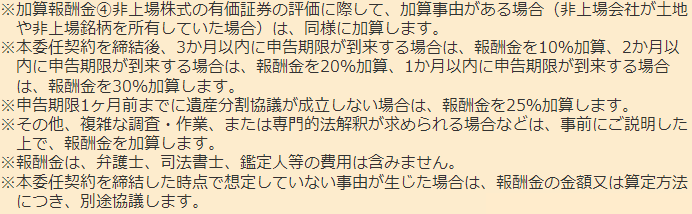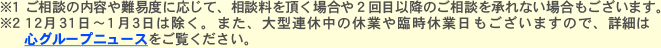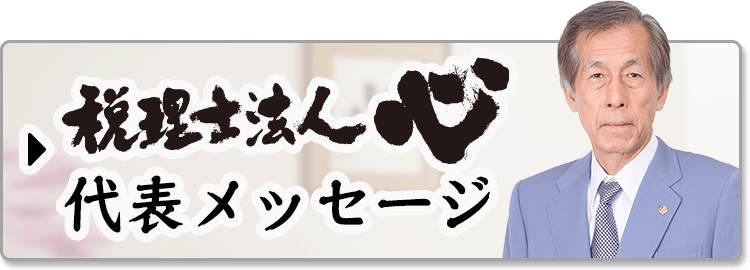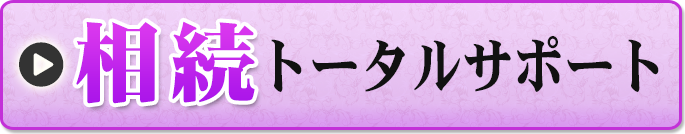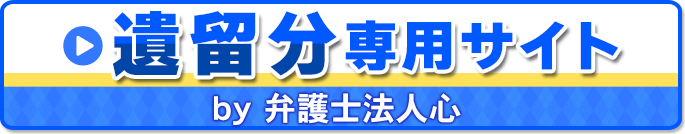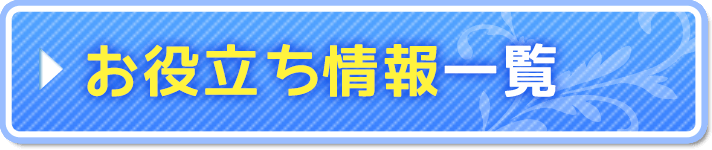お役立ち情報
相続税はどのように計算するのか
1 相続税の計算の仕方
相続税の計算は、課税遺産総額を算出し、いったん相続税の総額を算出したあとで、実際に取得した正味の遺産額の割合で按分します。
そのうえで、配偶者控除や各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算することになります。
2 課税遺産総額の計算
まず、相続や遺産によって取得した現金・預貯金、不動産、有価証券、動産等について、それぞれ資料を収集し、財産の評価をして「遺産総額」を算出します。
また、亡くなった方が、生前に子や孫などに対して財産を贈与して、相続時精算課税の制度を選択していた場合には、「相続時精算課税の適用を受けた財産の価額」も合計して計算します。
次に、前記の合計額から、債務、葬式費用、非課税財産(仏壇・祭具、国や地方公共団体等に寄付した財産、生命保険金のうち500万円×法定相続人の数、死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数)を差し引き、加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、「正味の遺産額」を算出します。
このような「正味の遺産額」が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、その超える部分が「課税遺産総額」となります。
たとえば、「正味の遺産額」が1億円で、妻と子2人が相続人であれば、1億円-(3000万円+600万円×3人)=5200万円が「課税遺産総額」となります。
3 相続税の総額の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
たとえば、課税遺産総額が5200万円で妻と子2人が法定相続分どおりに取得すると、妻は2分の1で2600万円、子はそれぞれ4分の1ずつで1300万円ずつとなります。
それぞれ税率や控除額が定められていますので、それを適用すると、上記のケースだと妻は340万円、子は145万円ずつとなり、合計630万円が相続税の総額となります。
4 実際に納める税額の計算
上記3のとおり計算した相続税の総額を、実際の相続割合に応じて按分します。
たとえば、妻が2分の1を取得したとすると315万円、子はそれぞれ4分の1ずつ取得すると157万5000円ずつとなります。
そのうえで、配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
配偶者の場合は、実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、相続税はかかりませんが、控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。
配偶者に対する相続税額の軽減 相続税で2割加算されるのはどのような場合か